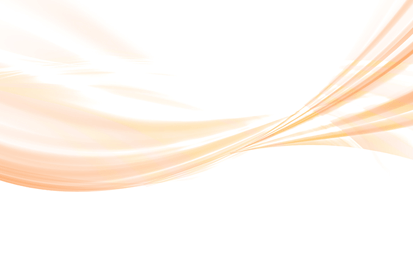障害者自立のための就労継続支援!人員配置の基礎を押さえよう

就労継続支援事業を適切に運営するために、人員配置についての基本を押さえておくことが大切です。特に、これから開業する場合であれば、必要な職種や人員数を知り速やかに人員確保をしなければなりません。すでに事業を運営している場合でも、報酬に影響する人員配置に関する変更点などを認識しておく必要があります。ここでは、職務ごとの人員数や基準を満たすために必要な要件、人員配置のポイントについて紹介します。
就労継続支援事業に必要な人員とは?
事業所すべてを管理する常勤の「管理者」は1名で、業務に支障がなければほかの職務との兼務も可能です。社会福祉主事任用資格の取得や、社会福祉事業に2年以上従事、または経営者としての経験が必要とされ、常勤であることは問われていません。個別指導計画に基づき障害者を支援する「職業指導員」と「生活支援員」は、それぞれ1名以上で常勤が1名以上と規定されています。事業の利用者数を10で割った人員が必要です。どちらも障害福祉の経験があることが望ましいとされていますが、特に資格の有無は問われていません。A型事業所における職業指導員は、就労の機会を提供しながら、一般企業の職場実習の開拓や就労後の支援も行います。生活支援員は、障害者が必要とする生活上の支援を提供します。
サービス管理責任者は利用者数60名以下で1名以上配置し、1名以上の常勤で専従であることが必要です。サービス管理責任者の業務を行うには、相談支援業務に5年以上、支援業務であれば10年以上の実務経験、サービス管理責任者研修を修了していなければなりません。サービス管理責任者は、就労継続支援A型計画作成アセスメントや利用者支援、職員への指導や助言を行います。サービス管理責任者を変更する場合には、サービス管理責任者としての要件を満たしているのかを確認することが必要です。新規事業所に対する経過措置は2018年3月に終了しているため、業務を行う際にはサービス管理責任者研修の修了証書が必要です。サービス管理責任者が退職するなどして不在の場合、事業所は新規の利用者を受け入れることができません。また、基本単位数や基本報酬のサー ビス管理責任者欠如減算などの措置がなされるため、できるだけ不在の期間を短くすることが大切です。
就労継続支援のA型とB型は何が違う?
障害者に就労の機会を提供する就労継続支援では、A型とB型の事業所区分があります。2種類の事業所の大きな違いとしては、「雇用契約」を結ぶ、結ばないという点に集約されるでしょう。就労継続支援A型事業は、一般の事業所に就労することが困難で、雇用契約による就労が可能な障害者が対象です。雇用契約を結んだ上で就労の機会を提供し、必要な知識や技能を身に付けるための支援を行います。就労継続支援A型事業所を運営するためには、雇用保険や健康保険などの保険を整えなければなりません。その分の運営費用はかかるものの、継続して雇用するメリットとして売り上げの伸びが期待できます。また、障害者雇用の助成金申請も見込めるでしょう。
一方、就労継続支援B型事業は、一般の事業所に就労することが困難で、雇用契約による就労も困難な障害者を対象に支援事業を行うものです。就労の機会を提供し、必要な知識や技術を身に付けるための支援をするのはA型事業所と変わりません。B型事業所は雇用契約を結ばないため、賃金や就労についての自由度が高いという特徴があります。また、支援の内容はA型よりもリハビリや訓練が中心になるので、売り上げには限界があることも、B型事業所を運営する上で押さえておきたい点でしょう。
基準を満たす人員配置のポイントは?
就労継続支援事業所を運営する際には、人員配置の指定基準を下回らないように気を付けなければなりません。それには、単なる人数のみを換算するのではなく、常勤と専従の考え方や職務ごとの要件を満たしているかを確認しておくことが大切です。常勤とは、事業所ごとに定められている常勤の時間数に達し、1週間に32時間以上勤務することが基準になる働き方です。1週間の勤務時間が32時間を下回る場合には、常勤とは見なされないことに注意が必要です。ただし、常勤の雇用形態は問われないので、正職員だけでなくパートタイムで業務を行う場合も1週32時間以上であれば常勤に含まれます。専従は、サービスに従事する時間帯には、指定されたサービス内容以外の職務を行うことができません。サービス管理責任者がほかの事業所と兼任していたために、専従・常勤の要件を満たしていなかった例もあります。
また、人員配置は前年度の利用者数の平均値に基づいて人員数が決まります。新規事業などで6カ月未満の事業所であれば定員の9割、6カ月から1年未満であれば直近6カ月の利用者数の平均が基準とされています。3カ月以上利用者が減少している場合は3カ月の平均利用者数です。そのほかにも「人員欠如減算」「加算要件」などの項目があるので確認しておきましょう。また、職員の退職や産休などにより人員配置に変化があった場合には、必ず人員配置基準を満たしているかを確認しなければなりません。非常勤職員の欠勤は、常勤に換算されないことにも注意が必要です。障害者が個々の能力に応じた自立を目指す就労継続支援事業は、人員配置を適切にして減算の対象にならないように配慮し運営したいものです。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
介護事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は18日、4月25日午後9時から一定期間、一部機能の利用を停止することを事務連絡した。電子請...
社会保障審議会・介護保険部会は21日、2040年に向けたサービス提供体制の在り方の議論を始め、人口減少が進む中山間地域などでサービスを維持・確保するため、常勤・専従要件などの配置基準の運用を条件付きで弾力化...
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で創設した「認知症チームケア推進加算」の要件となる認知症チームケア推進研修について、東京都が開発した「日本版BPSDケアプログラム」のアドミニストレーター養成研修で代替し...
厚生労働省は21日、匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)に格納されている介護レセプト情報などの第三者提供が始まった2018年度から24年度までの7年間で、提供件数が累計で49件あったことを社会保障審議会...
厚生労働省は21日、2026年度に施行される「介護情報基盤」で市町村による利用者の同意取得があれば、介護事業所は情報を閲覧するたびに同意を取得する必要はなく、また閲覧する事業所ごとに同意の取得する必要もない...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは