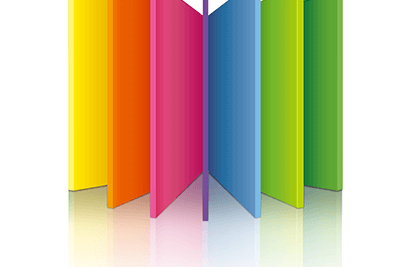介護ビジネスに参入する前に知っておきたい社会福祉法人の会計基準

日本の社会福祉の発展になくてはならない存在である、社会福祉法人ですが近年では株式会社を代表とする営利団体の福祉分野への参入や、特別養護老人ホーム内での内部留保額が問題になるなど、改めて社会福祉法人という存在を見直す転機が来ているようにも思われます。社会福祉法人はこれまでどのような役割を果たしてきたのか、今後はどうなっていくのか、見てみることにしましょう。
そもそも社会福祉とは?日本における社会福祉法人の歴史
日本の社会福祉の歴史は古く、さかのぼると1,500年以上の歴史を持つとも言われます。社会福祉法人制度が創設されたのは昭和20年代のこと。終戦後の混乱の中で引揚者、身体障害者、戦災孤児、失業者などの生活困窮者への早急な対応が求められた時代でした。政府に十分な資源がなく、民間資源の活用が求められた時代。そのような時代背景のもと、公的事業を行う団体として、社会福祉法人は設立されたのです。
その後昭和30年代から40年代にかけて、高度経済成長を背景に社会福祉制度の充実も進みました。社会福祉制度の専門分化が進み、生活保護法や児童福祉法、身体障害者福祉法など、いわゆる福祉六法が出揃ったのもこの時代です。昭和50年代以降になると高齢化や核家族化などが大きな社会問題として取り上げられるようになってきました。高齢者福祉分野でいえば、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が打ち出されたのが1989年になります。
近年におけるもっとも重大な変化は介護保険法の成立でしょう。これによって従来の措置制度による制限的なサービスから、保健制度による普遍的なサービスへと大きな転換が遂げられました。利用者がサービスを自分の意思で選択する契約制度がとられたことによって、介護サービスの種類や内容の多様化が進み、また経営主体も従来の社会福祉法人だけでなく、営利法人の活躍が目立つようになってきました。現在はこの流れの途上にあるといえるでしょう。
介護業界における社会福祉法人の在り方
このような背景を持つ社会福祉法人ですが、現在の介護業界ではどのような存在となっているのでしょうか?一番はこれまでと同様に、非営利法人として、市場原理では必ずしも満たされないニーズについて取り組むことを求められています。例えば過疎地域での福祉事業。一般の営利組織では手を出しにくい、こうした地域への福祉サービスの提供こそ、社会福祉法人に求められている大切な役割だといえるでしょう。営利事業のサービスからこぼれ落ちた人々を救うセーフティネットとして機能すること。とりわけ営利法人の活躍が目立つ昨今、この役割は社会福祉法人の社会的責務と言えるでしょう。
とはいえ、現実には多くの課題が指摘されています。制度創設当初から措置を受託する法人としての色彩が強く、行政の規制を強く受けていたため、現在でも非営利法人として制度や市場原理では満たされないニーズに取り組むよりも、行政指導に適合することに重きを置いた事業運営がなされていること。利用者本位のサービスを歌いながらも、そこに十分対応できていないこと。財務状況の不透明さや内部留保の増大など、制度や補助金、税制優遇によって守れた高い利益を地域に還元していない点など、その課題は多岐に渡ります。今後ますます社会福祉サービスの担い手が営利企業へと移っていくなかで、社会福祉法人の役割が改めて問われていることは間違いないでしょう。
公共性が高いビジネス特有の会計基準とは
では最後に、社会福祉法人特有の会計基準について述べておきましょう。社会福祉法人の会計基準は非常に複雑で、会計事務所に委託されていることがほとんどです。ここでは会計を構成する財務諸表および、社会福祉法人における会計基準の特徴について、簡単に紹介します。
財務諸表は「資金収支計算書」、「事業活動収支計算書」、「貸借対照表」の3つから構成されます。資金収支計算書とは、毎会計年度の支払資金の収支内容を明らかにしたもの。一般的な会計基準では、損益計算が導入され、事業活動収支計算書が重視されますが、収益よりも公益を重視する社会福祉法人においては、損益計算書よりもこちらのほうが経営状況を理解しやすいともいわれています。
事業活動収支計算書の目的は、事業活動の成果を明らかにすることです。一年間の事業活動の結果、どの程度の損益が発生したかを示したのがこの計算書になります。貸借対照表は法人の会計年度末におけるすべての資産、負債および純資産の状態を明確にするために作成が必要とされるものです。
社会福祉法人の会計基準にはもう一つ大きな特徴があります。それは、「拠点区分」という考え方。平成24年4月から27年3月までにすべての社会福祉法人で新会計基準への移行が義務付けられました。その際に導入された考え方で、他には事業区分、サービス区分という分け方も存在します。これは施設や事業所を一つの単位として考え、この単位ごとに財務処理を行う方法で、法人全体としての計算書だけでなく、これら各拠点区分、事業区分ごとの財務諸表が求められます。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
介護事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は18日、4月25日午後9時から一定期間、一部機能の利用を停止することを事務連絡した。電子請...
社会保障審議会・介護保険部会は21日、2040年に向けたサービス提供体制の在り方の議論を始め、人口減少が進む中山間地域などでサービスを維持・確保するため、常勤・専従要件などの配置基準の運用を条件付きで弾力化...
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で創設した「認知症チームケア推進加算」の要件となる認知症チームケア推進研修について、東京都が開発した「日本版BPSDケアプログラム」のアドミニストレーター養成研修で代替し...
厚生労働省は21日、匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)に格納されている介護レセプト情報などの第三者提供が始まった2018年度から24年度までの7年間で、提供件数が累計で49件あったことを社会保障審議会...
厚生労働省は21日、2026年度に施行される「介護情報基盤」で市町村による利用者の同意取得があれば、介護事業所は情報を閲覧するたびに同意を取得する必要はなく、また閲覧する事業所ごとに同意の取得する必要もない...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは