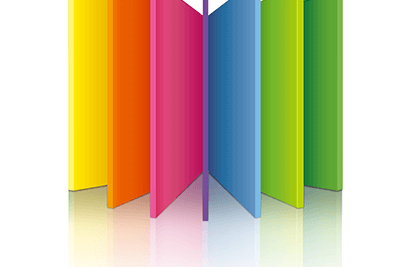将来ニーズに対応!有料老人ホームビジネスへの参入

介護事業の立ち上げを考える人の中には、有料老人ホームの設立を検討している人もいるでしょう。比較的開業が簡単だといわれる訪問介護事業所や通所介護事業所と比べると、開業時に莫大な資金が必要であり、その分だけリスクも高い事業です。ですがその一方で、介護報酬の切り下げによる影響が大きな通所介護事業所や利益率の薄い訪問介護事業所に比べると、運営が軌道に乗れば安定した収益が得られるのも、有料老人ホームの大きな魅力といえるでしょう。ここでは有料老人ホームを経営するにあたっての、注意点などを見ていくことにしましょう。
特別養護老人ホームと有料老人ホームの相違点
施設サービスの代表ともいえる、特別養護老人ホームと有料老人ホームとではどのような点が異なるのでしょうか?一番大きな相違としては、施設を経営する母体の違いが挙げられるでしょう。有料老人ホームは法人格を持っていれば株式会社でも設立が可能であるのに対して、特別養護老人ホームは社会福祉法人や公益法人などの非営利法人でなければ、設立が認められません。現在一般的な起業家が社会福祉法人格を取得する道のりは険しく、多くの起業家にとっては、有料老人ホームの設立を目指すのが現実的だといえそうです。
他にも違いはいくつかあります。特別養護老人ホームの場合、現在は要介護度3以上と認定された人でなければ入居することができませんが、有料老人ホームにはそうした条件はありません(施設によって独自の基準を設けているところもあります)。さらに社会福祉法人の場合、民間の利益に相当する余剰金を分配できない決まりがあります。そのため理事長が経営者として儲けを得ることはできません(理事長として働くことで、給与という形で報酬を受け取ることは可能です)。有料老人ホームの場合は一般的な株式会社と同様ですから、経営者としての利益を得ることができます。一方税制の面では社会福祉法人が大きく優遇されていることは間違いありません。ですが有料老人ホームの場合、居室代や食事代、それに入居一時金などを自己裁量で決められる分だけ、工夫の仕方次第では大きな収入につながるでしょう。
有料老人ホームを経営する前に知っておきたい基礎知識
次に、有料老人ホームの基本的な知識を確認しておきましょう。まずは有料老人ホームの形態です。一口に有料老人ホームといっても、その形態は多種多様。大きな区分としては、介護付きかそうでないかの違いがあります。一般的な特養と同じように、直接雇用しているスタッフが24時間介護をする形態を、一般型特定施設入居者生活介護と呼びます(特定施設と呼ばれることもあります)。簡単にまとめてしまうと、介護付き有料老人ホーム=特定施設と考えても概ね間違いないでしょう。
介護付きでない有料老人ホームとして、住居型と健康型の2種類が存在しています。住居型とは、介護が必要になった場合は入居者自身の選択によって、地域の訪問介護や通所介護サービスを受けながら、生活をしていく施設のこと。近年成長著しいサービス付き高齢者住宅(通称:サ高住)もここに含めることができるでしょうか。一方で健康型とは、介護が必要になった場合には契約を解除し退去することが求められます。
有料老人ホームの開設には大きな困難が伴います。代表的な困難としては、入居者の確保、職員の確保、開業資金の確保、以上の3点が考えられます。開業資金については次で取り扱うとして、ここでは前者2つについて見ていくことにしましょう。
一昔前であれば、老親を見てもらえればどんな施設でも構わない、と考える人が少なからず存在しました。ですが現在は、施設サービスも競争が激化しています。入居を決定する側も、事前にしっかりと情報収集をして、コストに見合うサービスが受けられる施設を求めています。多くの大企業が参入している有料老人ホーム事業で、生き残ろうと思えば独自色を出していくことが求められるでしょう。
そのためには人材の確保が欠かせません。介護事業を行うにあたって多くの経営者が頭を悩ませることになるのが、介護人材の獲得。現場で働く一般職員も管理職も、すべてが不足しているのが介護業界。有料老人ホームだけでなく特別養護老人ホーム、それに通所介護や訪問介護。すべての事業所が血眼になって、優秀な人材を探しています。
ビジネス参入のための融資と補助金制度
最後に開業のための融資や補助金制度について見てみましょう。有料老人ホームは、開業時にまとまったお金が必要となります。その金額は訪問介護事業所や通所介護事業所とは比較になりません。物件の取得から建物の建設費用、什器類や備品の用意、顧客や職員獲得のための営業費用などなど。すべてを合わせるとおよそ2億5千万円~3億円は必要というのが、一般的な相場のようです。
これだけの資金を個人で用意するのは簡単なことではありません。となると当然融資や補助金を申請する必要がでてくるでしょう。現在サービス付き高齢者向け住宅の開設にあたっては、国からの補助金交付の対象となっていますから、有効活用したいもの。サ高住以外では国からの補助はないため、融資に頼ることになります。
リスクが大きい分だけ大きな見返りが期待できる有料老人ホームビジネス。ですが安定した経営をするためにはさまざまな障害を乗り越える必要があります。とりわけこれまで介護事業の経験がない場合、その苦労は並大抵のものではありません。ですが壁が高ければ高いほど、乗り越えた先の景色はすばらしいもの。社会的な貢献度も高い事業が、今日も誰かのチャレンジを待っています。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で創設した「認知症チームケア推進加算」の要件となる認知症チームケア推進研修について、東京都が開発した「日本版BPSDケアプログラム」のアドミニストレーター養成研修で代替し...
厚生労働省は21日、匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)に格納されている介護レセプト情報などの第三者提供が始まった2018年度から24年度までの7年間で、提供件数が累計で49件あったことを社会保障審議会...
厚生労働省は21日、2026年度に施行される「介護情報基盤」で市町村による利用者の同意取得があれば、介護事業所は情報を閲覧するたびに同意を取得する必要はなく、また閲覧する事業所ごとに同意の取得する必要もない...
社会保障審議会・介護保険部会は2月20日、次期介護保険制度改正に向けたテーマとして、地域包括ケアシステムにおける相談支援のあり方や、認知症施策の推進について議論した。前者では、居宅介護支援事業所と地域包...
介護福祉士とは、専門的な知識と技術を生かし、介護サービスを利用する人の心身のケアを行ったり、現場で働く従業員の指導・育成を行ったりする職員のことです。介護現場にとってなくてはならない存在ですが、介護福...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは