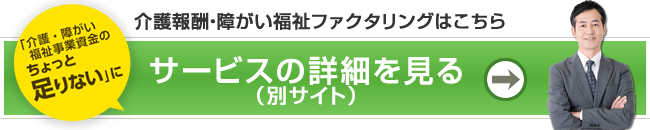若年性認知症支援コーディネーターって何?制度や役割についてしよう

認知症というと高齢者の病気というイメージを持たれがちですが、実際には若者が発症するケースも珍しくありません。介護事業者は、そのような患者をサポートする若年性認知症支援コーディネーターの設置に関心を持っている事業者も多いでしょう。そこで今回は、若年性認知症支援コーディネーターの制度や役割などを紹介します。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
1.若年性認知症支援コーディネーター設置事業について
若年性認知支援コーディネーターの設置事業を推進しているのは、主に都道府県です。国の策定したプランには、各都道府県ごとに相談窓口を設置し、認知症に悩む人を支えるネットワークを調整するための調整役として存在することが書かれています。段階的にサポートの範囲を広げて、市町村とも連携していくのが基本的な方針です。そのため、介護事業者は研修を行い支援に必要な知識やスキルをスタッフに習得させつつ、自分は事業主として自治体と協力しながら設置に必要な取り組みを進めることになります。
2.若年性認知症コーディネーターって何をする人
若年性認知症は、症状によって必要なサービスが異なります。したがって、画一的な方法で対応していくことが難しく、かつては本人や家族が満足するケアを受けられないケースもありました。そのような事態を招かないために、若年性認知症コーディネーターは患者や家族が必要なケアを受けられるよう、ニーズを把握することが主な仕事です。さらに、各関係機関との連絡調整を行うなど、若年性認知症コーディネーターは若年性認知症に関する幅広い支援を行っています。
3.若年性認知症コーディネーターの役割
若年性認知症の人が自分らしい生活を送れるよう、福祉的な観点からさまざまなコーディネートをしていくことが、若年性認知症コーディネーターの役割です。たとえば、就労していた人が発症した場合、コーディネーターは医療機関や福祉団体だけでなく、職場などにも働きかけることで居場所を失わないように配慮します。また、本人や家族の心のよりどころとして相談に乗ることも非常に重要です。そのため、困っていることを察知したり、いち早くニーズに応えたりするなど、さまざまな方法で信頼を築いていく必要があります。
4.若年性認知症コーディネータ―の主な業務内容
具体的な業務としては、本人や家族に対する個別支援の相談窓口が挙げられます。話を聞いて現状を把握したうえで、利用可能な補助制度に関するアドバイスや医療機関とアクセスし継続的に支援していくなど、適切な対応をしなければなりません。また、市町村や他の機関と連携する体制を築くことも代表的な業務です。本人や家族に接する関係者には、若年性認知症に関する情報を提供することも必要です。本人の残存能力や適性を見極め、医師と連携しながら社会復帰を促していく就労支援も業務のひとつになります。
5.若年性認知症とは
認知症は発症した年齢によって名称が変わります。18~44歳の場合は若年期認知症、45~64歳の場合は初老期認知症と呼ぶのが一般的です。若年性認知症はこのふたつを合わせたもので、64歳以下の人が発症したケースの総称です。この年齢層の人たちは、家庭や職場で中心的な役割を果たしているケースが少なくありません。したがって、それ以上の高齢で発症する認知症とは別に、早期回復を可能とする重点的なサポートを求める声が増えているのです。
6.症状
若年性認知症の症状は大きく2種類に分けられます。1つ目は脳に関する症状で、記憶力の著しい低下に代表されます。新しいことから忘れていくのが特徴で、進行すると数分前の体験も覚えていられなくなります。また、場所や時間を認識することが苦手になるのも特徴です。2つ目の症状は心に関するもので、理由もなく不安や憂うつな気持ちになってしまいます。幻覚や幻聴によって怯えるようになったり、妄想に取りつかれて性格が変わったりするケースも少なくありません。
7.原因
年齢に関わらず、認知症は脳に関する病気が主な原因です。若年性認知症も基本的には同じで、脳腫瘍や脳血管障害といった病気によって引き起こされるケースが多いのです。若年性認知症の大きな特徴としては、アルコールの飲み過ぎや頭部の外傷など、脳に直接関係する病気以外の要素が関係しているケースも多いことがあげられます。このように多様な原因があるのは、年齢的に活動的な人が多いと言う背景もあげられます。
8.対処法
若年性認知症の対処として大切なのは、なるべく早いうちに治療を受けることです。しかし、まだ若い人は自分が認知症であるという発想に至りにくい場合があります。ミスや物忘れが増えても、仕事や家事による疲れのせいにしがちです。記憶力などに違和感を覚えることがあり、それが短期間で払拭されないなら、脳神経内科や心療内科などで精密な検査をしてもらうのが望ましいでしょう。発症していた場合、周囲の人は十分な気遣いをしなければなりません。落ち浮いて過ごせるように、本人の心情を察しながら、ゆっくりと接していく必要があります。
介護の資金繰りにはファクタリング
若年性認知症支援コーディネーターの設置に興味あっても、資金力が不足している介護事業者は、人員の確保や教育の面で後れをとってしまうことがあります。介護報酬が入るまでの期間が長く、資金繰りに困っている場合、介護ファクタリングサービスを利用してみるのはいかがでしょう。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
介護事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は18日、4月25日午後9時から一定期間、一部機能の利用を停止することを事務連絡した。電子請...
社会保障審議会・介護保険部会は21日、2040年に向けたサービス提供体制の在り方の議論を始め、人口減少が進む中山間地域などでサービスを維持・確保するため、常勤・専従要件などの配置基準の運用を条件付きで弾力化...
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で創設した「認知症チームケア推進加算」の要件となる認知症チームケア推進研修について、東京都が開発した「日本版BPSDケアプログラム」のアドミニストレーター養成研修で代替し...
厚生労働省は21日、匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)に格納されている介護レセプト情報などの第三者提供が始まった2018年度から24年度までの7年間で、提供件数が累計で49件あったことを社会保障審議会...
厚生労働省は21日、2026年度に施行される「介護情報基盤」で市町村による利用者の同意取得があれば、介護事業所は情報を閲覧するたびに同意を取得する必要はなく、また閲覧する事業所ごとに同意の取得する必要もない...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは