
2018年に介護報酬が改定される!どんなことが起きる?
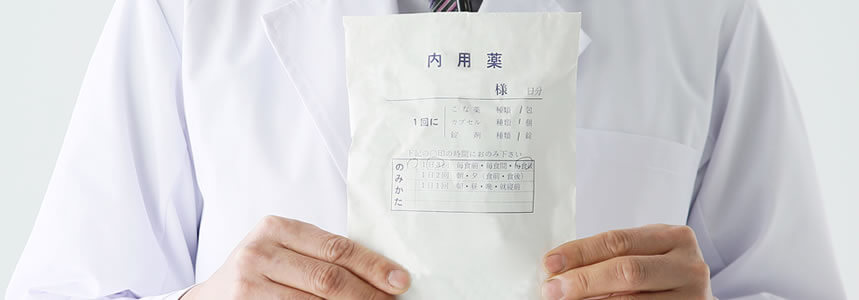
2016年8月2日、介護者の月額給与が平均で1万円相当改善されることが閣議決定されました。この決定が施行されるのは2018年からですが、介護事業を行っている経営者はそれまでにその閣議決定の中身をよく理解しておく必要があります。また、日本では2025年には団塊世代が後期高齢者と呼ばれる75歳を迎えます。現在でも、社会保障費の国庫負担は国家予算の3分の1を占めるほどです。このままではさらに出費が増えてしまうと予想されるため、2018年度の制度改正には社会保障費を抑えられるような案が盛り込まれています。こちらについてもよく知っておく必要があります。
具体的に変わる項目はどんなものがある?
介護保険制度は、急激に進む少子高齢化といった社会的問題を受けて作られた制度です。そのため、担当の厚生労働省でさえ、「走りながら考える」と答弁するほどの見切り発車で始まりました。結果的に6年に一度、制度を見直して改正することを原則としており、2006年には「予防・地域密着」、2012年には「地域包括ケア」といった概念を提唱してきたのです。ただし、例外的に2015年には社会保障費の増大を受けて「高額所得者の自己負担2割」を実施するなどといった制度改正が行われています。つまり、例外を実施するほど現在の社会保障費の国庫に占める割合は増大しており、2025年には団塊世代が後期高齢者になることによってさらに苦しい運営が迫られているのです。
2018年の改正には、介護報酬改定により月額給与を平均で1万円上げるといったこと以外にもいくつか重要な施策がありますが、基本的には社会保障費に負担をかけずに今までのサービスをできるだけ維持していくことに目的がおかれています。具体的には「施設から在宅へ」といった流れを今以上に加速させることです。
2017年現在、生活に不自由な人を介護する介護者は人手不足状態にあります。今後、高齢者が増えていくにつれて何も対策を打たないでいると、ますます人手不足が進んでしまう事は明らかであり、2025年には38万人もの人材が不足するといわれています。そのため、政府としてはできるだけ寝たきりの介護者を減らすために、慢性疾患や病気による機能低下を抱えながらも、それらと付き合いながら生活の質(QOL)を保つ支援に重点を置いているのです。
介護者の報酬はどうなる?
介護報酬改定は「月平均で1万円程度上昇させる」ことを目的としています。これは介護職が他の業種と比べても比較的低賃金であることだけでなく、今後増加する高齢者に対して介護職の待遇をよくすることで、できるだけ介護者を確保しておくという目的があります。報酬アップの中身については、これまでになかった経験の長さや職務といったキャリアアップによってもらえる給与が上がるという仕組みになっています。これまでは提供する介護サービスの種類によって一律に給与が定められていたため、勤務歴が長いベテランでも勤務歴の浅い若手でも同じ賃金ということになっていました。この部分を改善することによって、介護者の仕事に対するモチベーションを上げる目的があるとされています。
この給与基準は「新加算1」といわれますが、適用されるためには条件があります。その条件は基本的には介護福祉士などの資格を持っている人を想定していますが、事業所で独自に設けた基準でも問題ありません。その基準は「キャリアパス要件3」と呼ばれ、その内容を就業規則などの書面にして全職員に周知する必要があります。キャリアパス要件3は勤続年数などの「経験」、介護福祉士や実務研修修了者などの「資格」、実技試験や人事評価といった「評価」の3つのうち、いずれかに該当した場合に昇給することができるとされています。また、昇給について基本的には「基本給による昇給が望ましい」とされていますが、手当や賞与といった部分で支払うことも問題ないという点は覚えておきましょう。
離職率にはどう影響する?
2018年の介護報酬改定によって賃金が上昇することは、介護者にとってメリットです。また、ただ単に賃金だけが上昇するだけでなく、「経験」、「資格」や「評価」といったこれまでにない要件を導入したことによって、介護者のモチベーションを上げることができ、仕事に対するやりがいを感じさせるものになるでしょう。しかし、上昇する賃金は月額1万円です。賃金が上がることは、その仕事を続ける上でもちろん大きなメリットになりますが、介護の仕事は労働環境として大変であることを考えると、必ずしも離職率が低下するとは言い切れません。
また、賃金が上昇する背景になったことは、そもそも介護職の給与が他の業種と比べて低かったからです。今回の引き上げでようやく他の業種と同程度の給与になったという考え方もできます。そのため、介護職の離職率を低下させるためには、さらなる賃金の上昇による介護職の世間的なステータスのアップや、労働環境の改善といったことを行うことが必要です。このような点が改善されない限り、介護職の離職率が大きく改善する可能性は低く、今後も介護士の人手不足が続くことでしょう。
2018年の介護報酬改定は現状の介護職の待遇を改善することだけが目的ではなく、2025年もしくはそれ以降の日本を見据えた内容になっています。今後も少子高齢化が進み社会保障費の増大は避けては通れません。社会保障費の負担を減らすために、施設型の介護から訪問型の介護へ徐々に政策が移行する可能性がありますので、経営者の方は動向を注視しておく必要があるといえるでしょう。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
財務省は23日に開かれた財政制度等審議会・財政制度分科会で、介護事業者などが人材紹介会社を利用する場合に高額の紹介手数料を支払っているケースがあるとし、不適正な紹介会社の排除を徹底するよう提言した。さら...
社会保障審議会・介護保険部会は2月20日、市町村に要介護認定審査期間の短縮化を促す取り組みの案を了承した。平均認定審査期間や認定審査期間が30日以内の割合などを市町村別で公表するほか、認定審査の各プロセス...
介護事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は18日、4月25日午後9時から一定期間、一部機能の利用を停止することを事務連絡した。電子請...
社会保障審議会・介護保険部会は21日、2040年に向けたサービス提供体制の在り方の議論を始め、人口減少が進む中山間地域などでサービスを維持・確保するため、常勤・専従要件などの配置基準の運用を条件付きで弾力化...
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で創設した「認知症チームケア推進加算」の要件となる認知症チームケア推進研修について、東京都が開発した「日本版BPSDケアプログラム」のアドミニストレーター養成研修で代替し...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは







