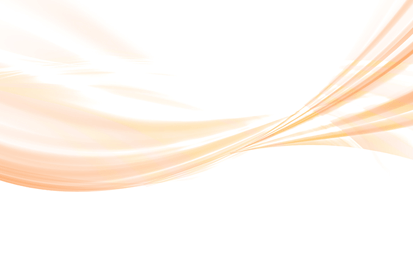介護ロボットの導入で日常生活動作の改善を目指すには?!

ロボット関連技術が進化した結果、さまざまな分野でロボットが活躍するようになっています。なかでも、介護分野でのロボット活用が注目されている状況です。介護の現場では、介護する人の労働力の負担軽減や、日常生活動作改善サポートなどの目的で、すでに多くロボットが活用されています。
そこで、介護ロボットとはどんなものなのか、具体的にどんな種類のロボットが活用されているか、さらには介護ロボットを導入することで日常生活動作の改善は可能なのかについて解説します。
介護ロボットとは
介護事業経営者や経営者候補のなかには、介護ロボットをすでに導入してどんなものであるかを把握している人もいれば、介護ロボットとはこんなものだというイメージがないという人もいるでしょう。じつは、介護ロボットには、「これが唯一の定義」というものはまだありません。厚生労働省が公表している「福祉用具・介護ロボット開発の手引き」では、介護ロボットを「ロボット技術を活用した福祉用具」と位置づけています。福祉用具とは、介護を必要とする人の助けになる道具、もしくは自立支援につながる道具です。また、同じく厚生労働省が公表している別の資料では、情報感知や判断、動作の3つの要素を持っており、自律的判断を行う機械システムのうち、利用者の自立生活支援や介護者の介護負担軽減に役立つ機器を介護ロボットと位置付けています。
さらに、センサーによる感知を行い、自律的に判断・制御し、駆動系をもって動作するものを介護ロボットだというのがロボット産業振興に努めている経済産業省「ロボット政策研究会」の定めです。民間団体のなかには、介護ロボットを「介護サービスを支援する先端機器やシステム」と定義している団体もあります。これらを考慮すると、介護ロボットとは、介護を必要としている人だけでなく、介護サービスを行う人もサポートするものであり、センサー機能と自立判断機能、動作機能を持つものであると理解すればよいでしょう。
どんな介護ロボットがいる?
介護ロボットを導入するにあたっては、どんな種類の介護ロボットがあるのかを知っておくことも重要です。介護を必要とする人が自ら行う動作や介護する人の支援動作にはさまざまな動作が含まれます。一般的な介護ロボットは、各動作に特化したものが多いということが特徴です。主な介護ロボットを6つ紹介します。
1つ目は、移乗介護型介護ロボットです。ベッドから車椅子、トイレの便座などへの乗り移る動作を支援するロボットで、要介護者が身に着ける装着タイプもあれば、ロボットが要介護者を抱える動作を行って支援するタイプもあります。
2つ目は、排泄支援型介護ロボットです。排泄物処理や排泄動作をサポートします。トイレの時間を予測して要介護者を誘導する機能などがあることが特徴です。
3つ目は、入浴支援型介護ロボットです。浴槽への出入りや湯船に浸かる動作をサポートする機能があります。入浴は安全に配慮して行う必要があるうえ、力を必要とする作業です。ロボットの導入で入浴サポートが楽になります。
4つ目は、移動支援型介護ロボットです。外出や屋内での移動をサポートします。体に装着するタイプや姿勢の維持を支援するタイプなどです。
5つ目は、見守り・コミュニケーション型介護ロボットです。話し相手になったり、徘徊を察知したりする機能があります。
6つ目は、機能訓練型介護ロボットです。安全に立ち上がることをリフトでサポートしたり、装着することで歩行動作に関する負荷を軽減したりする役目を果たします。
介護ロボットの導入で日常生活動作の改善は可能?!
要介護レベルによっては、状態が改善して日常生活動作ができるようになる可能性があります。そういった状況にある場合は、できるだけ自立した生活ができるようにサポートすることが重要です。介護ロボットのなかには、歩行や食事、排泄、入浴など日常生活動作の改善に役立つ可能性があるロボットもあります。リハビリなどの機能訓練に役立つことを目的としてロボットを活用すれば、日常生活動作ができるようになるでしょう。
また、状態が改善しなかったとしても、ロボットの機能を活用して日常生活動作をしやすくするという方法も有効です。たとえば、歩行することをサポートする機能があるロボットを簡単に装着できれば、要介護者自ら装着して歩行できるようになるでしょう。操作する人の意思を適切に駆動部分に伝えて、ロボットの力と本人の力をうまくミックスする機能も向上しているため、より使いやすくなってきています。
ロボットは、工場などの生産ラインで活躍する産業実需で発展してきました。しかし、ロボット技術の進化によって、生活をサポートするロボットも登場してきています。AI(人工知能)の発達によって、センサーで得た情報を的確に処理する技術も高くなってきているため、介護ロボットの性能は向上中です。日常生活の動作がスムーズにできるようなることに役立つだけでなく、介護をするスタッフの負担軽減や労働環境改善にも役立ちます。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
介護事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、厚生労働省は18日、4月25日午後9時から一定期間、一部機能の利用を停止することを事務連絡した。電子請...
社会保障審議会・介護保険部会は21日、2040年に向けたサービス提供体制の在り方の議論を始め、人口減少が進む中山間地域などでサービスを維持・確保するため、常勤・専従要件などの配置基準の運用を条件付きで弾力化...
厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で創設した「認知症チームケア推進加算」の要件となる認知症チームケア推進研修について、東京都が開発した「日本版BPSDケアプログラム」のアドミニストレーター養成研修で代替し...
厚生労働省は21日、匿名介護保険等関連情報データベース(介護DB)に格納されている介護レセプト情報などの第三者提供が始まった2018年度から24年度までの7年間で、提供件数が累計で49件あったことを社会保障審議会...
厚生労働省は21日、2026年度に施行される「介護情報基盤」で市町村による利用者の同意取得があれば、介護事業所は情報を閲覧するたびに同意を取得する必要はなく、また閲覧する事業所ごとに同意の取得する必要もない...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

 けあコンシェルとは
けあコンシェルとは